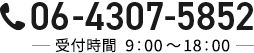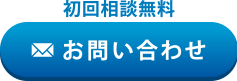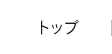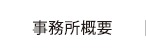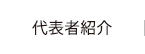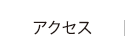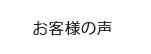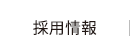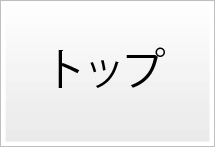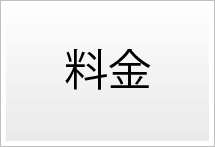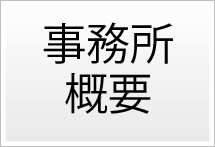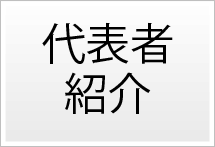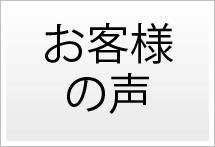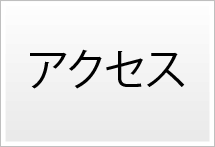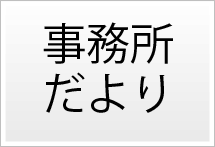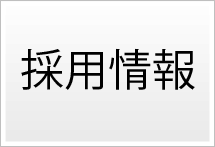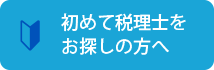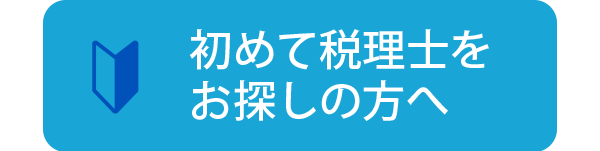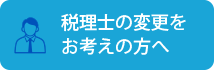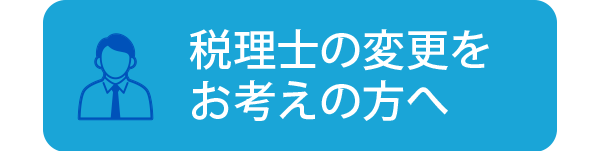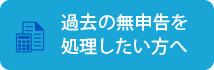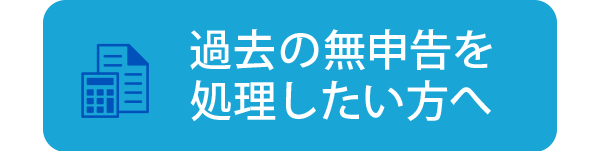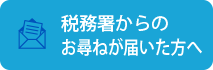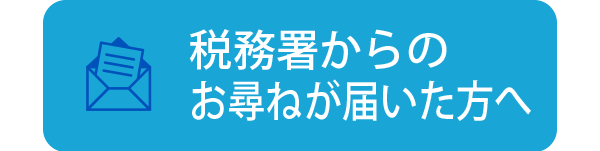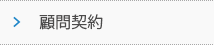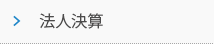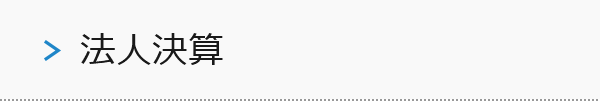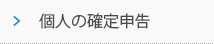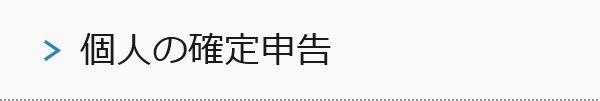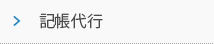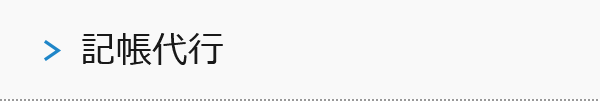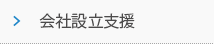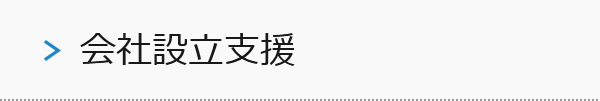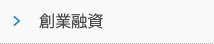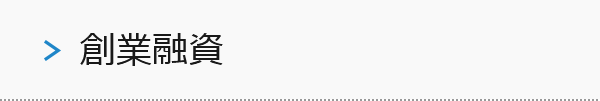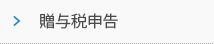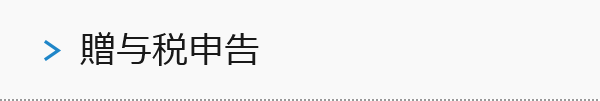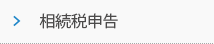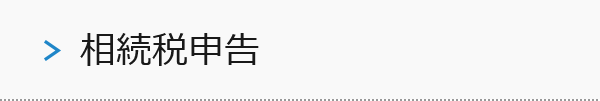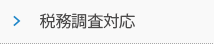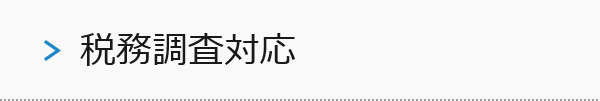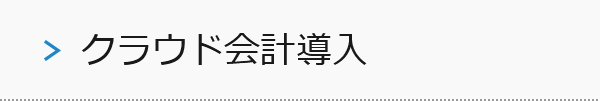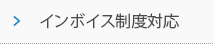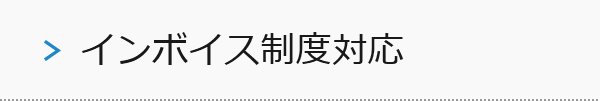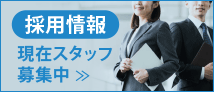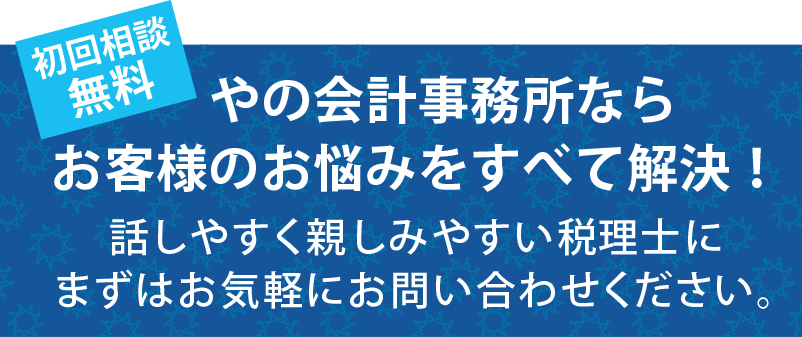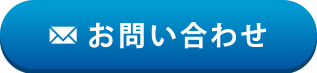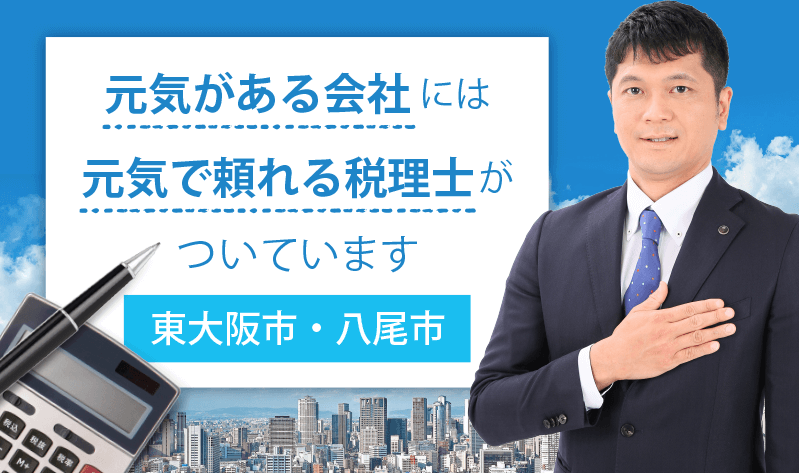
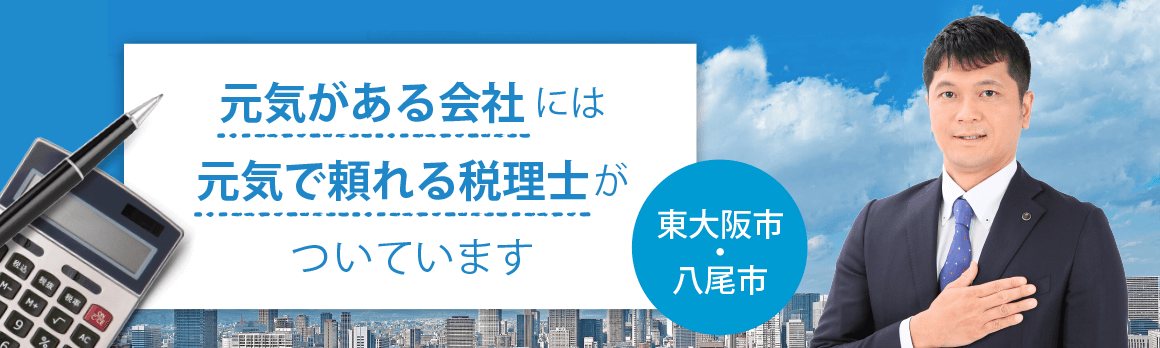
事務所だより
東大阪の税理士事務所が、法人の保険加入を考える。

会社経営をされていれば、
一度は保険加入をご自身で検討したり、
税理士や知人の営業の方から勧められたりした事が
あるのではないでしょうか。
保険は商品のラインナップも多く、
契約内容も複雑です。
そのため、保険営業の方や詳しそうな税理士の
勧めるがままに加入される方も多いのではないでしょうか。
中には、ご自身の加入内容を把握せずに
無駄な保険料を支払い続けている方もおられます。
個人に至っては保険は人生の5大支出にも入ります。
一度加入すると見直す機会もあまりないので、個人も法人も
加入前に正しい考え方を知っておかれるべきです。
ここでは、東大阪の税理士事務所・やの会計事務所が
お客様が保険の加入を考える際に、
必ずアドバイスすることをお伝えします。
保険商品の個別の取扱いではなく、
根本的な考え方を中心にお伝えします。
1.保険は、どうして加入する?
保険の目的は、将来起こりうる様々なリスク(病気、事故、災害など)に備え、
不測の事態が発生した場合に、経済的な損失を補うためです。
法人経営は、あらゆるリスクを負っています。
そのリスクのうち、起こる可能性が低いが、
起きてしまったら、企業の存続に関わるものに、
一定のコスト(保険料)を支払って備えます。
つまり、リスクが無いなら、本来加入する必要はないです。
また、コストも同じ保障をうけるなら保険料は
低い方を絶対に選択すべきです。
当然の考え方ですが、
保険の加入の際に、この考え方が抜けておられる
経営者の方が多くみられます。
2.保険に加入して得することはある?
保険で得することは、基本的に「ない」です。
保険事故(死亡や病気)が起こった場合に、
保険金が支払われますが、これは得ではなく損失への補填です。
マイナスの事象を0に戻すだけです。
これにより儲かるわけではないです。
一応、例外的に得したっぽい話は、よく耳にします。
保険会社の事故審査が甘く、損害以上に
保険金が受け取れたなどです。
ただ、これらは偶然で、これを期待して
加入するのは目的からかなりズレると思います。
その他、節税や解約返戻金に利回りが付くといった
お得っぽいお話もあります。
では、それぞれの観点で見ていきます。
3.法人保険が「節税」になる仕組み
法人の経営者は保険加入を提案される際に、
「節税」につなげて提案される場合があります。
お得そうなお話です。
保険で節税ってどういうことなのか?
法人加入の保険は一定の要件を満たせば、
支払い保険料のうち一部を経費として計上することが可能です。
(損金の計上額は保険内容によります。ここでは詳しいお話は割愛します。)
そして、保険契約によっては、掛け捨てではなく、
途中解約した場合に、解約返戻金が支払われるものがあります。
この仕組みを活かして、保険料を支払って、
保険会社にお金を預けているようにして、
その分経費に計上し、利益を少なくするのことで、
節税につながるとされています。
ただし、この解約返戻金は将来受け取った際には、
利益になります。
保険料として支出時に、経費としていた代わりに、
戻ってきた解約返戻金は利益になるのです。
結局は、利益を先送りにしただけになります。
しかも保険料は、毎年毎年の経費ですが、
解約返戻金は一括支払われますので、多額の利益になります。
この解約返戻金を受け取った際に、
代表者の退職金費用などに充てられれば
納税をうまく回避できますが、
解約時点で経費がうまく計上できなければ
まとめて課税されることになります。
4.節税が昔の話
保険契約によって、以前は支払保険料の全額や50%を
経費に計上することが認められていました。
しかし、2019年にこの節税保険に規制が入りました。
一定以上の解約返戻金を予定する保険契約について、
保険料の経費算入が縮小されることになりました。
現在では、最も経費に計上できるもので、
解約返戻金を85%を上限に、保険料の40%経費に算入するものが
主流になってきています。
各社これに合わせて商品を作っているのですが、
これはどう考えても使い勝手が悪いです。
節税効果は、(軽減税率適用の会社の場合)実効税率が23%
×40%で、保険料の9%程度しか節税ができません。
保険料を支払って、その9%節税されて、85%の解約返戻金
しか戻らないければ実質的に損していることになります。
この解約返戻金の目減り分15%は、保険料相当とされますが、
保障額と見合っているか検証が必要です。
掛け捨てでこの半分以下の保険料でも
保障が確保できる場合はあります。
5.投資商品として利用できるか?
最近が一時払いの保険契約がよく売れていると聞きます。
これは解約返戻金がほぼ100%戻される代わりに損金は認められません。
特徴は保険料を一時払で契約し、
その保険料を米国債等で運用し解約時に利回りをのせた返戻金を戻すものです。
保険機能は薄く、運用に傾いたものです。
これも個人的にはあまりお勧めしません。
保険本来の目的と異なるものが、
付帯しているからです。
保障額は、支出する保険料に対しては小さく、
運用利回りも決して高いとは言えない、
保険と投資をミックスした中途半端な商品です。
保険を買うなら、必要な保障額の保険契約をする。
運用利回りが目的なら、優良な投資ファンドを購入する。
これが鉄則です。
6.賢く利用する
保険を検討する際には、まずは最初の目的通りに、
いくら保障が必要なのかを見積もることです。
この見積りは、各会社の状況によりますので、
絶対的なものはありません。
ご自身が、もしもの時にいくら保障されれば、
危機を回避できるのか、それぞれで見積もることが必要です。
例えば、1億の借入金があり、経営者がお亡くなりになって、
経営が滞ることを考えれば1億の保障が必要かもしれません。
しかし、返済の目途が十分にたつ経営をしているのであれば、
保障は半分以下でもいいでしょう。
一度大雑把にでも、リスクと予見される損害を
見積もることが重要になります。
そのうえで、コストを抑え保険を賢く利用しましょう。
7.最後に
今回は保険について、基本的な考え方をお伝えしました。
法人の保険契約は、保険料も大きく、
保険会社が各社、色々な商品を開発しています。
中には、節税効果が誇張され、実質的の損するものや、
保険とは関係のない運用利回りが強調されたものがあります。
保険は、会社経営に安心と継続保障を与えてくれます。
そのためには一定のコスト負担は必要ですが、
必要以上の加入は避けるべきです。
やの会計事務所では、保険についてもアドバイスさせて頂きます。
お客様のリスクを一緒に見積、必要な保険を提案し又は、過度な保険の解約、
を提案しております。
ご自身の保険加入状況に疑問を感じられる方が是非ご相談ください。
令和7年7月4日
執筆者:税理士 矢野修平(https://yanotax.com/staff.php)