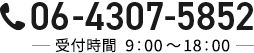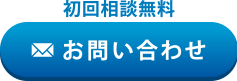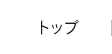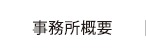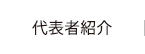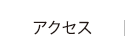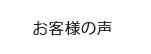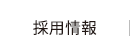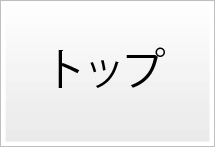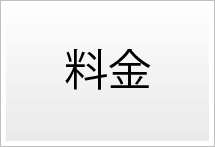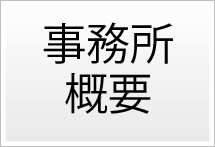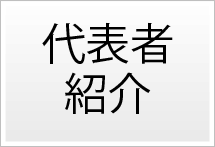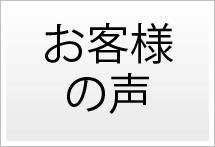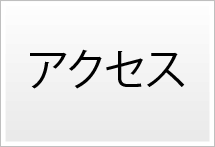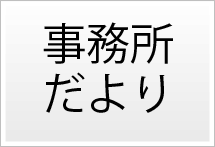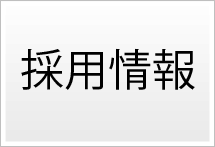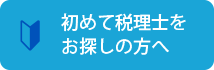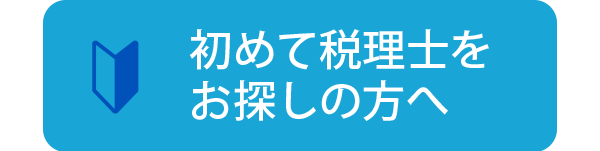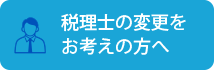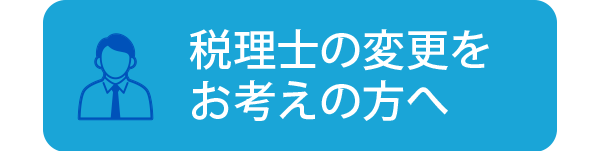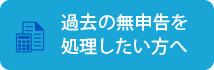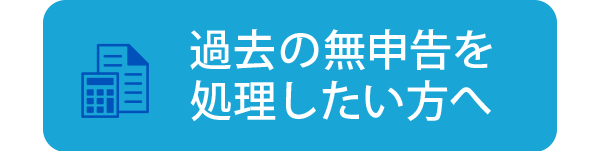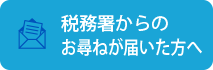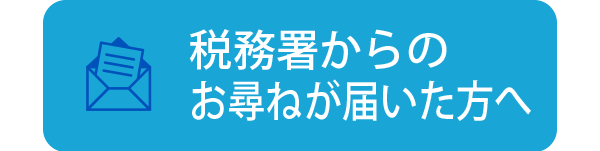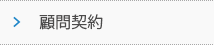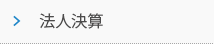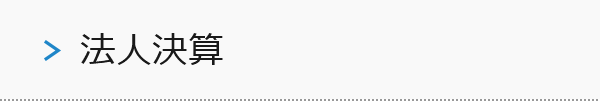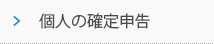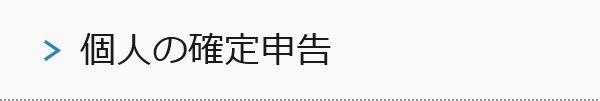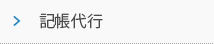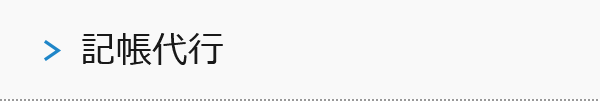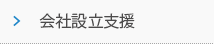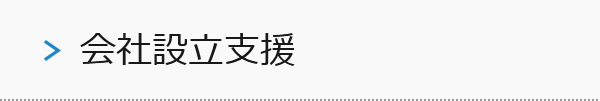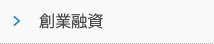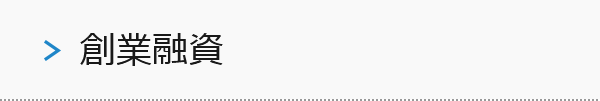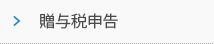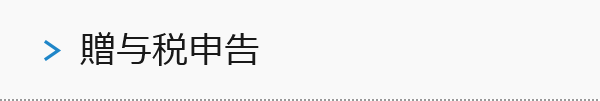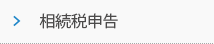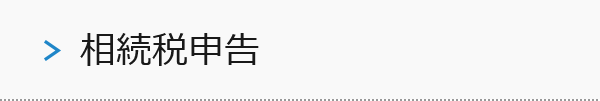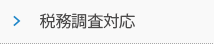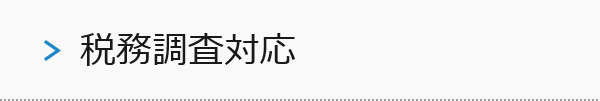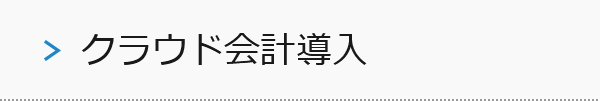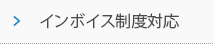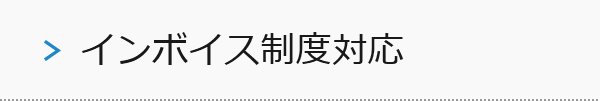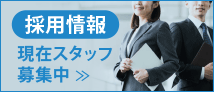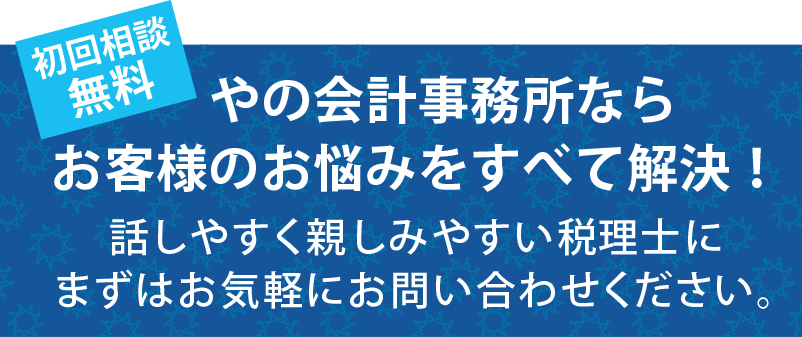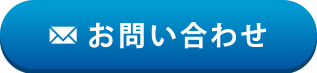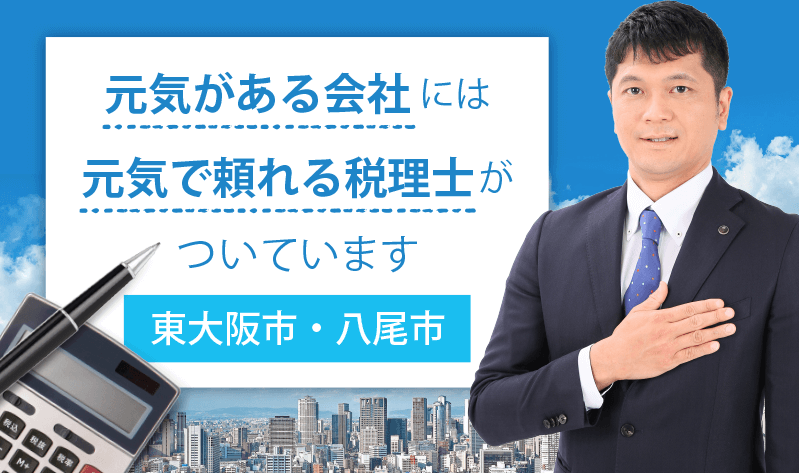
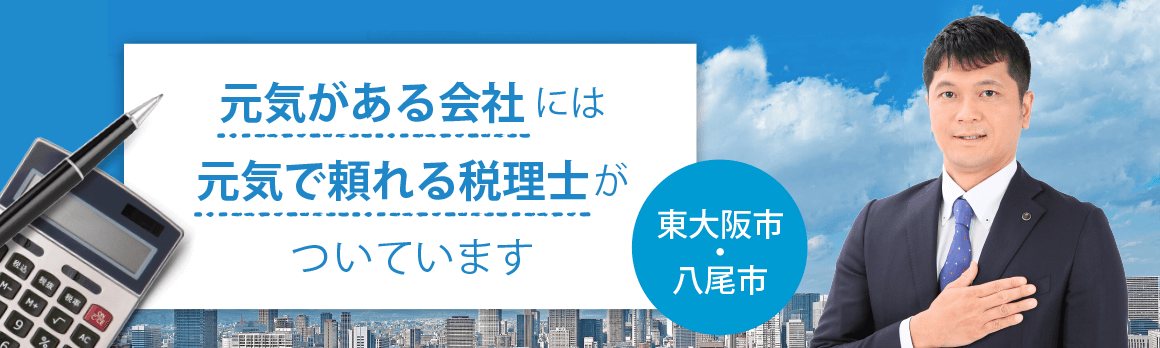
事務所だより
東大阪の税理士が教える!│決算賞与で節税

こんにちは、東大阪の税理士 やの会計事務所です。
梅雨が明けて、本格的な夏がやってきました。
今年は例年に増して厳しい暑さのようです。
この時期に話題になるのが、夏のボーナスです。
世間では去年に比べて、ボーナスの増減が話題になります注目されます。
経営者も、ボーナスをどのくらい支給してあげたらいいのか
悩まれる方も多いかと思います。
このボーナスについて、夏季賞与、冬季賞与が一般的ですが、決算時にも
決算賞与という形でボーナスを支給する会社もあることをご存知でしょうか。
この決算賞与は、節税対策としても利用されます。
そこで今回は、「決算賞与の支給検討」という節税策をご紹介します。
節税の基本は「経費を適切に計上して利益を圧縮すること」です。
しかし、機械や車両の購入などの高額な支出は、減価償却という考え方から数年に分けて
経費計上されますので、支出時に全額を経費にできないことが多く、また決算”直前”では
効果を発揮し難い節税策が多いです。
この点、決算賞与は金額を柔軟に決められ、かつ決算ギリギリでも
活用できるとても便利な節税策になります。
1. 決算賞与の節税効果とは?
決算賞与とは、決算日以前に支給する賞与のことで、
法人税法上の経費として扱うことが可能です。
この制度の魅力は大きく分けて以下の4点です。
• 賞与として経費に計上でき、利益を減らせる。(=節税効果)
• 賞与のほか、それに付随する社会保険料(会社負担分)を
未払経費として計上できる。(=節税効果)
• 給与と賞与の合計額が前期より1.5%以上増えた場合、付随して
所得拡大促進税制の適用が可能になる。(=節税効果)
• 従業員のモチベーションアップ、待遇改善につながる。
2.節税成功のための注意事項
(1) 原則として、決算日までに支給する。(要件を満たした場合、未払計上可能)
法人の経費に計上できる賞与は、原則として決算日までに支給されたものに限られます。
ただ、決算間際に急遽決めた賞与について、予算の問題や支給額の計算など
忙しい決算日までに支給することは難しくなる場合もあります。
そういった場合には、次の3つの要件を満たして決算日以後の支給でも経費計上が可能です。
【賞与が未払いでも認められる3要件】
要件① 決算日までに従業員へ支給額を通知していること
要件② 決算日から1ヶ月以内(翌月末まで)に支給を完了すること
要件③ 賞与を「未払費用」として正しく計上すること
⇒要件①の従業員への通知は、書面やメールなど、
後日、適切な通知をしたことが確認できるようにしておくことが重要です。
口頭での通知は税務調査で否認される可能性が高いため、必ず証拠資料を残しましょう。
(2) 賞与だけでなく、付随する社会保険料の資金準備が必要になる。
賞与は、給与と同様に社会保険料が課されることとなります。
賞与支給後5日以内に年金事務所へ届出を行い、賞与を支給した翌月末に
社会保険料(賞与額の約30%)が徴収されます。
この点も踏まえ、賞与の予算の目安を(賞与額面+会社負担分約15%)
見積もっておく必要があります。
また、この予定される社会保険料のうち会社負担分も未払で経費計上できます。
この賞与を支給した場合の、年金事務所への届出については、
よく漏れるポイントですので、注意が必要です。
(3) 代表取締役やその他役員には適用できない。
決算賞与のご提案をすると、社長自らのボーナスのお話もされます。
しかし、残念なことに、役員に対する賞与は、原則として経費にできません。
賞与支給はできるのですが、経費として取り扱いが認められないのです。
そのため社会保険や源泉所得税などの負担だけが発生してしまいます。
(4) 決算賞与の支給理由をしっかり説明。
今期の決算賞与を支給理由については、従業員さんに説明するようにしてください。
これは来期も同じように支給できるかどうかは約束できないからです。
「今期は、業績がよかったから特別に」ということを伝えましょう。
従業員さんの立場では来年もどうしても期待してしまうものです。
せっかく支給したのに、逆効果にならないように注意が必要です。
また、各会社の就業規則や労働契約によりますが、
決算賞与を既定の賞与の前払いとすることも考えられます。
例えば、10月決算で毎年12月に賞与を出している法人の場合、
決算賞与として10月に支給後、残りを12月の賞与支給するのです。
これなら、当初の賞与予算も変更せず、従業員さんも早く支給されるので、
問題も生じにくいでしょう。
ただし、来期計上できる賞与を今期に計上しているだけ(経費の先取り状態)ですので、
今期の節税はできますが、来期の利益増(=税額の増加)につながる点は注意が必要です。
3. 実際に支給する上でのポイント
実務でのおおまかな流れを整理しておきます。
① 利益の概算を把握する
→税理士や会計担当者と相談し、利益の着地を予測します。
② 対象者と支給額を決定
→社内規定がある場合はそれに従い、公平性・合理性に配慮します。
③ 決算日までに支給を完了
→銀行振込で行い、証拠が残るようにしておきます。
(決算日までに支給できない場合)
・通知書の作成と通知の実施
→「○月○日に△△円支給予定」などと明記した通知書を従業員へ配布。
従業員の署名をもらうのがベストです。
・通知文書の保管
→税務調査に備えて、書面やメールをしっかり保管しておきましょう。
・決算日翌月末までに支給を完了
→銀行振込で行い、証拠が残るようにしておきます。
④ 支給後、5日以内に年金事務所へ「賞与支払届」を提出
→社会保険料が発生するため、忘れずに届け出が必要です。
4. 事例紹介(弊社顧問先より)
弊社が顧問を務める東大阪市にある建設業の法人(12月決算)では、
10月に所得の予測を立てたところ600万円前後の所得が見込まれました。
12月に入り大きな受注があったとのことで、再度所得の予測を見直したところ、
冬季賞与を支給した後でも、所得がおよそ800万円~900万円ほどになると予測されました。
法人税は、所得が800万円を超えると超えた部分の所得に対する税率が
約10%(国税、府民税、市税含む)上がります。低い税率を維持できるような節税策で、
かつ決算前1ヶ月を切った状態で有効なものとして、社長へ決算賞与を提案させていただきました。
社長にも従業員へ還元してあげたいという思いがあったようで、
決算賞与に対して前向きに検討頂きました。通常の賞与と併せて、
12月の賞与が2回となり従業員からの反応も良好だったそうです。
節税効果も相まって、社長も満足されました。
5. 最後に
決算賞与は、「決算ギリギリでも間に合う」数少ない節税手段の一つです。
しかし、正しい運用・記録が伴わない場合には、経費として認められないリスクもあります。
また、賞与支給後には社会保険料が発生するため、賞与額の設定や
利益の見通しも慎重に検討すべきです。
決算直前で慌てないためにも、早めの利益予測と制度の活用計画が鍵となります。
東大阪の税理士事務所、やの会計事務所では、顧問サービスの範囲内で、
以下の内容も実施しております。
・節税施策のご提案
・決算賞与の実行支援
・決算賞与の支給の様な節税策の実行支援
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
執筆担当者:税理士 矢野修平