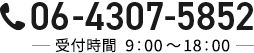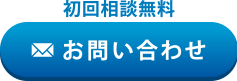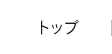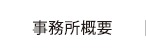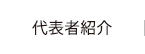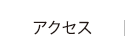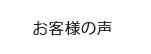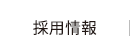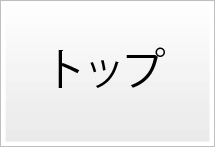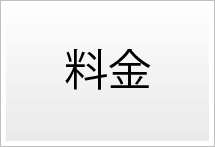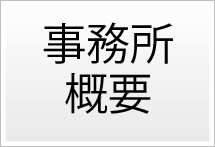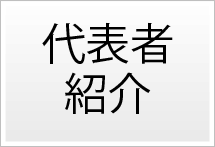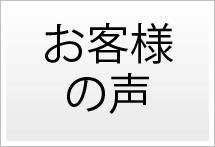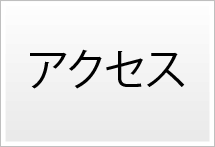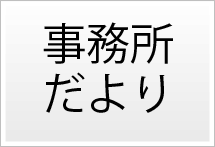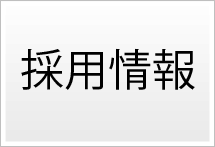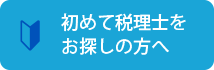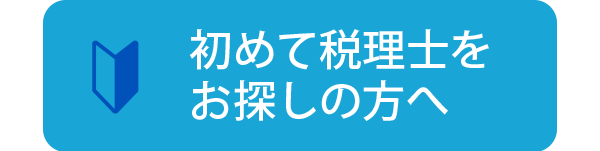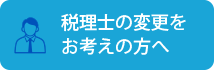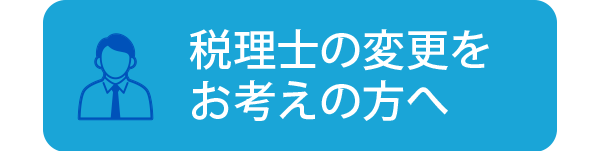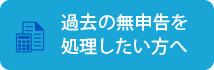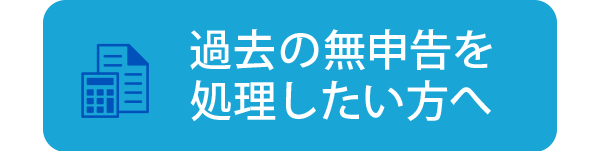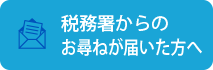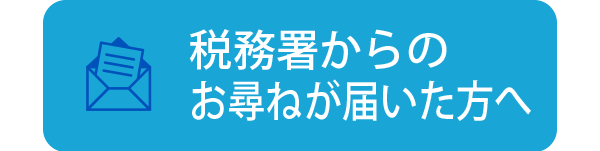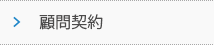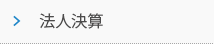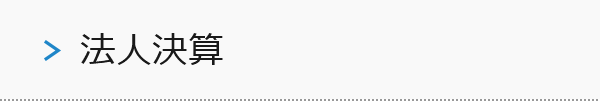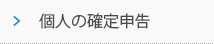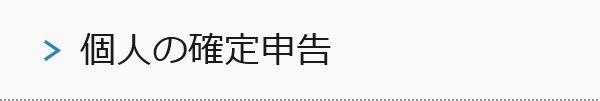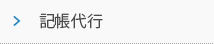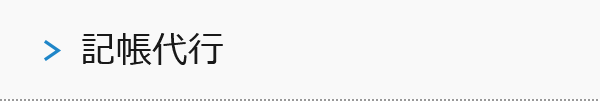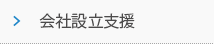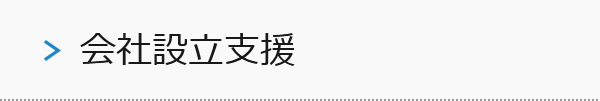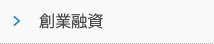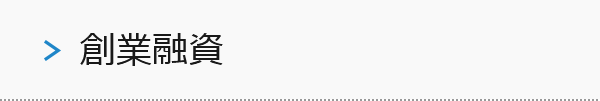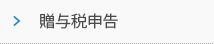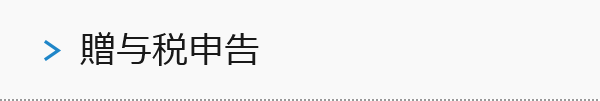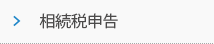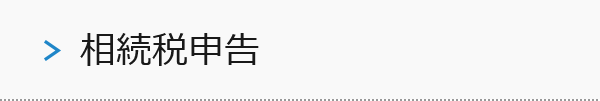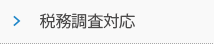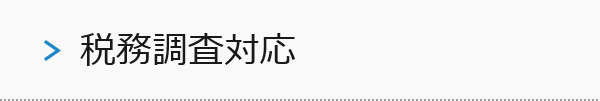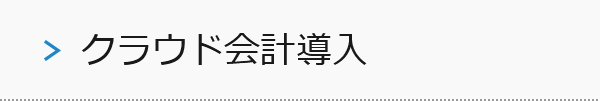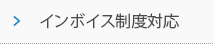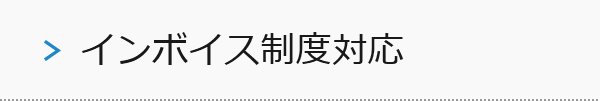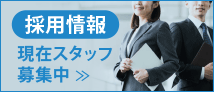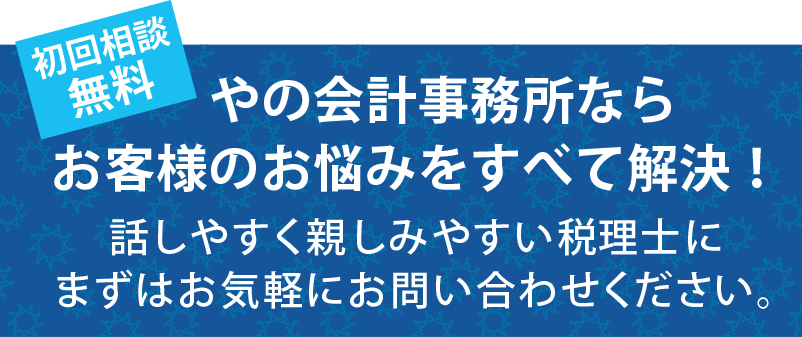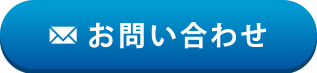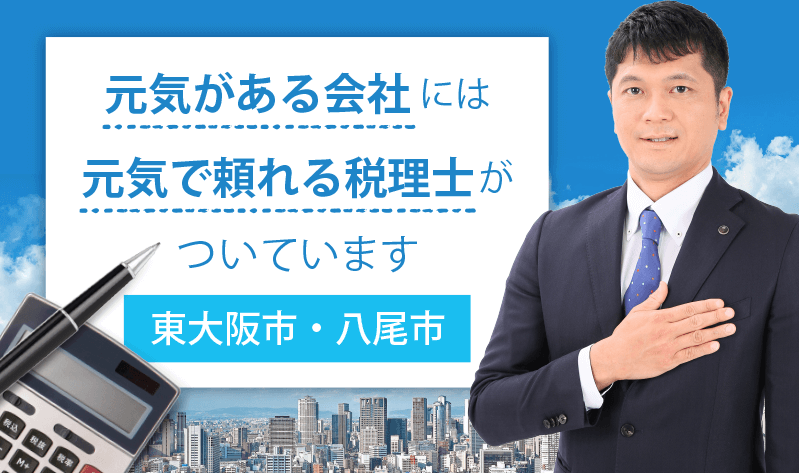
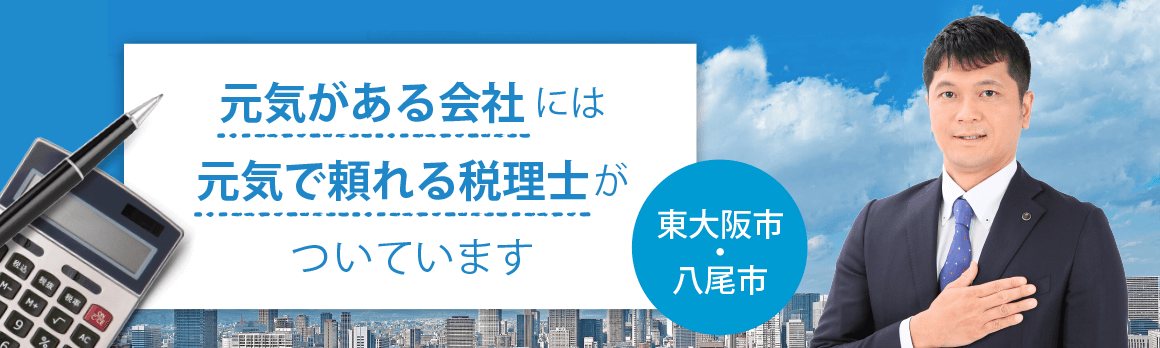
事務所だより
【税務署からのお尋ね】が届いた!

こんにちは。東大阪の税理士 矢野です。
7月に入り、本格的な夏が始まりました。
この時期になると、毎年、税務署に動きがあります。
税務署では人事異動が行われ、新しいチームが組織されます。
そして翌年の6月末までの1年、そのチームで
税務調査に取り組んでいきます。
この時期から【税務署からのお尋ね】という文書が、
特定の人に郵送されます。
本日はその【税務署からお尋ね】文書についてのお話です
無機質な封筒に、税務署からの手紙が入っています。
手紙の内容は概ね、こんな感じです。
=============================
××× 様
あなたには、●●に関する取引履歴があります。
この取引について、申告されていないですが?
その理由は?
理由なく申告していないのであれば、
取引内容のわかる書類(通帳や請求書、経費の領収書)などを
用意して税務署にきてください。
×××税務署 担当:税務太郎
=============================
要約すると、こういうことです。
「取引履歴はこちらでほぼ把握しているから、
無申告を適正にしてください」
いきなりの、税務署からの通知に驚かれて、
戸惑われるかと思います。
この書面でやってはいけないことは、無視することです。
無視した場合には、もう一度通知がくるか、
税務署から電話がかかってきます。
それでも無視し続けるとある日突然、ご自宅や営業所に
調査担当者が来訪します。
ここまでくると、よくわからないまま税務署側主導で
話が進んでしまいます。
では、この税務署からのお尋ねにどのように対応したらいいのか・・・?
1.なぜこんなお尋ねが届くの?
①一般資料せんで判明
国税局では毎年、様々な情報を収集しています。
代表的なものは「一般資料せん」といわれるものです。
事業者に対して一定の条件で郵送します。
この書面で「取引先等」や「取引規模」報告させることを義務付けます。
「買った人がいれば売った人がいる」
売り手買い手両方の側面から取引実態を確認し、
それぞれの申告の有無や、妥当性を判断しているのです。
②税務調査で判明
税務調査では、調査先の取引先を詳細に記録します。
実際、調査の現場では個人の外注先などの名称や住所など
調査官がメモされているのをよく見ます。
これらの記録で、相手側の申告の有無を確認し、
申告がなかったら、お尋ねが送られる対象になります。
③その他にも
これは憶測になりますが、Amazonやメルカリなどの
プラットホームなどに取引データの開示を求めているのではないかと思います。
そのうえで、継続して取引している事業者の申告の有無を確認し、
申告漏れしている人を抽出していると考えられます。
2【税務署からお尋ね】が届いた場合の対応方法
①現状の把握
お尋ねに記載されている「取引」が実際にあるかどうか、
まずは確認しましょう。
取引の収入からそれに伴う費用(仕入や経費)を差し引いて
利益がでていれば、本来申告の必要があります。
これは、手元の不用品や中古品の処分で収入があった場合を
除き取引が継続していればご本人の認識に関わらず申告の
対象になります。
ただし、利益の金額が軽微な数字の場合には申告が省略できる場合があります。
その場合でも、税務署側は、かかった経費の内容までは
把握していないので、その旨は連絡する必要があります。
②期限までに連絡
お尋ねの内容に概ね心当たりがあれば、必ず記載された期限までに
連絡しましょう。
担当者に来所する日時や持参する書類など指示されると思います。
この時「どうしても税務署に電話する気になれない」
「どのように話を進めていいかわからない」といった
不安のある方は、税理士に相談して頂くことも可能です。
税理士は「税務代理権限証書」という書類を提出することで、
納税者の方に代わってお話を聞くことが可能になります。
税務署に連絡するまでには一度検討してみてください。
③税務署で面談
税務署での面談の際には、一連の取引内容がわかる書類
の持参が求められます。
面談の場では、申告書の書き方や税金の計算方法など指示されます。
調査官によっては、無申告のついて、その理由を問い詰め、
厳しい指摘をされる場合もあります。
また、過去複数年の申告をしていない場合には、
資料が不足していたり紛失していることも考えられます。
その場合には、調査担当者が合理的な計算方法で、
納税額の計算を進めます。
この時、税金の計算についてあまり詳細にわかっていなければ、
税務署主導で進められることになります。
④納税
③である程度の話がまとまれば、納税に向けて進みます。
過去の支払うべき納税額のほか、無申告加算税などの
ペナルティの含め納付が求められます。
3 税理士がサポートできること
①税理士が納税者の代理に
税務署とお話する機会はそんなに多くはないと思います。
そのため、できれば誰かに代わって欲しいものです。
先にも述べました通り、税理士が全て代理で、「税務署への連絡」から、
「申告書の提出」までお手伝いできます。
税務署に本人の来署を要請される場合もありますが、
その場合も、税理士の同席も認められるので
不安に感じられる方にとっては、心強いかと思います。
すぐにでも、代理を希望される方は、お尋ねの右下に記載してある、
「管轄税務署」「担当部署」「担当者」の名前を
税理士に伝えるようにしてください。
②申告書作成サポート
お尋ねに記載されている通りに取引がある場合には、
一般的には自主申告による納税が求められます。
申告書は納税者本人が作成することになります。
日常忙しくされている中、売上や経費の集計は、
大変な労力がかかると思います。
税務署側にも期限が設定されると思います。
税理士であれば申告書の作成まで、
スムーズにサポートしてもらえます。
③納税額の妥当性の交渉
無申告の場合であれば、申告して相応の税金を支払うことが仕方がないです。
ただ、先にも述べました通り、過去の分の申告については、
本来かかっていた経費などのエビデンスが紛失していることも多いです。
その場合、調査担当者の方はヒアリング等で、
合理的に計算を進めます。やはり、税務署サイドは、徴税不足が無いよう、
白黒はっきりしないモノは、税金が多くなるように計算しようとします。
そのため、納付税額が多くなりがちです。
また、税務署の税額が決まれば、自動的の地方税(住民税など)が
決定します。さらには個人の場合は、
国民健康保険などの負担増につながる場合があります。
税理士が入れば、地方税等の負担も勘案しながら、
税務署にできる限り税額が少なくなるよう交渉します。
4 お尋ねで、「他人にバレない?」
税務署からのお尋ねが来た場合に、税務署以外に、
「他人にバレない?」といったご質問をよくいただきます。
勤務先に内緒で副業している場合もあったり、
元請けの会社への信用の問題にもつながるからでしょう。
この件はご安心ください。
基本的には税務署との間でお話が完結するのが一般的で、
通報されたりなど、考えられません。
ただし、お尋ねを無視し続け、最終的に税額が決定され、
さらに納税にも応じない場合には、「滞納処分」になり、
最終的には給与の差し押さえになります。
そうなりますと、勤務先に通知が行きます。
早めに適切な対応が望ましいです。
5 最後に
今回は「税務署からのお尋ね」について、ご紹介しました。
この記事をお読み頂いている方に中には、
実際に手許に届いている方もおられるのではないでしょうか。
適切に対処すれば、1か月ほどで問題は解決します。
また、しっかり対応した後は、そのお仕事も続けられます。
もし、税務署からのお尋ねが届いて一人で悩んでおられましたら、
是非、東大阪にある税理士事務所「税理士法人 やの会計事務所」に
お問合せください。
東大阪周辺だけではなく関西一円全ての税務署の案件に対応しております。
令和7年7月4日
執筆者:税理士 矢野修平(https://yanotax.com/staff.php)
【関連ページ】
税務署からのお尋ねが届いた場合:https://yanotax.com/ask.php
過去の無申告を処理したい方へ:https://yanotax.com/undeclared.php